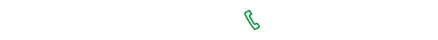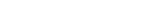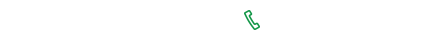やる気が出ないときに強制的にやる気を出す3つの方法
「今日は勉強する気になれない…」
そんな日、ありますよね。
お子さんが机の前に座っても、ボーッとしているだけ。
「やる気が出ないなら無理にやらせても意味がない」
そう思っていませんか?
でも、実は。
やる気は、「やる前」じゃなくて「やった後」に出てくるものなんです。
今日は、35年間で10,000人以上を指導してきた私が、やる気が出ないときに強制的にやる気を出す3つの方法をお伝えします。
方法1:勉強する前に10分散歩する
なぜ散歩がやる気を出すのか?
これ、科学的に証明されているんです。
早めのリズムでトントンと足を動かすことで、強制的にドーパミンが出るんですよね。
ドーパミンとは、「やる気ホルモン」のこと。
これが出ると、自然と「やりたい!」という気持ちになります。
イリノイ大学の実験結果
イリノイ大学の実験によると、
運動後に勉強した人は、記憶力が25%も上がった
という結果が出ています。
25%ですよ!
これは、ものすごい効果なんです。
具体的なやり方
1. 勉強する前に10分散歩する
外に出て、早めのリズムで歩く。
トントンと足を動かす。
これだけです。
2. 家の中でもOK
外に出られない日は、家の中で足踏みでもOKです。
音楽をかけて、リズムに合わせて足を動かす。
これでもドーパミンが出ます。
3. 毎日の習慣にする
勉強の前に10分散歩。
これを習慣にすると、体が「散歩したら勉強する」と覚えます。
自然とやる気が出るようになるんですよね。
実際の効果
私の塾の生徒で、こんな子がいました。
毎日「やる気が出ない」と言って、机の前でボーッとしている子。
そこで、勉強の前に10分散歩させることにしたんです。
最初は「え〜」と嫌がっていましたが、1週間続けたら。
「なんか、散歩した後の方が頭がスッキリする!」
と言い始めました。
そして、1ヶ月後。
散歩なしでは勉強できない、というくらい習慣になったんです。
やる気が出ないと言っていた子が、自分から勉強するようになりました。
方法2:行動スイッチを決める(やる前のルーティン・儀式)
行動スイッチとは?
「これをやったら勉強する」という儀式を決めることです。
例えば:
- コーヒーを一口飲んだら勉強する
- 机の上を拭いたら勉強する
- 好きな音楽を1曲聴いたら勉強する
これを決めておくと、体が自動的に「勉強モード」に入るんですよね。
なぜ行動スイッチが効くのか?
人間の脳は、「パターン」が好きなんです。
同じ行動を繰り返すと、次の行動が自動化されます。
「コーヒーを飲む → 勉強する」
これを繰り返すと、コーヒーを飲んだ瞬間に、脳が「次は勉強だ」と認識するんです。
やる気を出そうと頑張らなくても、自然と勉強モードに入れます。
具体的なやり方
1. 自分だけの儀式を決める
何でもいいんです。
- ストレッチを5回する
- 深呼吸を3回する
- ノートを開いてペンを持つ
自分が「これなら毎回できる」というものを選んでください。
2. 毎回必ずやる
ここが大事です。
毎回、必ず、同じ儀式をやる。
これを続けることで、脳がパターンを覚えます。
3. 1ヶ月続ける
最初の1週間は効果を感じにくいかもしれません。
でも、1ヶ月続けると、確実に変わります。
儀式をやっただけで、自然と勉強モードに入れるようになります。
実際の例
私自身も、行動スイッチを使っています。
私の場合は、「机の上を拭く」。
これをやると、自然と仕事モードに入ります。
やる気が出ない日も、まず机を拭く。
すると、不思議なことに「じゃあ、やるか」という気持ちになるんですよね。
方法3:まずは5分だけ始める
やる気は、やった後に出てくる
これ、多くの人が勘違いしているんです。
「やる気が出たら、やる」
じゃなくて、
「やったら、やる気が出る」
が正解なんですよね。
作業興奮の法則
心理学で「作業興奮」という言葉があります。
これは、行動を始めると、脳が自然と興奮状態になるという法則です。
最初は嫌々でも、始めてしまえば、自然とやる気が出てくるんです。
だから、まずは5分だけ。
とにかく始めることが大事なんですよね。
具体的なやり方
1. 「5分だけやろう」と声をかける
「今日は1時間勉強しなさい」
これは、ハードルが高すぎます。
「5分だけやろう」
これなら、子どもも「5分ならできる」と思えます。
2. タイマーを5分にセット
スマホやキッチンタイマーで5分セット。
「5分経ったら終わっていいよ」
と言ってあげてください。
3. 5分後に確認
5分経ったら、「もうやめる? それとも続ける?」と聞いてください。
不思議なことに、ほとんどの子が「続ける」と言います。
なぜなら、すでに作業興奮が起こっているからです。
実際の効果
私の塾の生徒で、こんな子がいました。
「1時間勉強しなさい」と言うと、全くやらない子。
そこで、「5分だけやろう」と声をかけることにしたんです。
最初は「5分だけね!」と確認しながら始めました。
でも、5分経った時に「もうやめる?」と聞くと、
「もうちょっとやる」
と言うんです。
そして、気づけば30分、1時間と勉強していました。
「5分だけ」のハードルの低さが、やる気を引き出したんですよね。
この3つの方法を組み合わせる
この3つの方法、実は組み合わせると最強なんです。
最強の組み合わせ
ステップ1:勉強する前に10分散歩する → ドーパミンが出て、体が活性化
ステップ2:行動スイッチ(儀式)をやる → 脳が「勉強モード」に入る
ステップ3:まずは5分だけ始める → 作業興奮で、自然とやる気が出る
この3ステップで、やる気が出ない日でも、確実に勉強を始められます。
具体的なスケジュール例
19:00: 夕食後、「10分散歩に行こうか」 19:10: 散歩から帰ってくる 19:12: 行動スイッチ(机を拭く、ストレッチなど) 19:15: 「5分だけやろうか」とタイマーをセット 19:20: 5分経過。「続ける?」→「うん!」 19:50: 気づけば30分以上勉強していた
このパターンを作ると、毎日スムーズに勉強が始められます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 毎日散歩しないとダメですか?
できれば毎日がベストですが、難しい日もありますよね。
その場合は、家の中で足踏みでもOKです。
大事なのは、「体を動かすこと」。
これでドーパミンが出ます。
Q2. 行動スイッチは途中で変えてもいいですか?
最初の1ヶ月は、同じ儀式を続けてください。
脳がパターンを覚えるまで時間がかかります。
1ヶ月経って、効果を感じられたら、別の儀式に変えてもOKです。
Q3. 5分で終わっちゃうこともありますか?
あります。
でも、それでもいいんです。
「5分やった」という事実が大事。
明日もまた「5分だけ」から始めればいいんです。
継続が最重要です。
まとめ:やる気が出ないときに強制的にやる気を出す3つの方法
改めて、今日のポイントをおさらいします。
方法1:勉強する前に10分散歩する → 強制的にドーパミンが出る → 記憶力が25%UP(イリノイ大学の実験)
方法2:行動スイッチを決める → やる前のルーティン・儀式 → 脳が自動的に「勉強モード」に入る
方法3:まずは5分だけ始める → やる気は、やった後に出る → 作業興奮の法則
この3つを組み合わせると、やる気が出ない日でも、確実に勉強を始められます。
あなたのお子さんも、この方法で必ず変わります。
同志社香里、関大一中への逆転合格も夢じゃありません。
今日から、ぜひ試してみてください。
京大卒/35年間で10,000人以上を合格に導いた 逆転合格指導プロ 斉藤